障害者雇用の担当者は、障害者雇用に関する法律や手続きなどたくさんの新しい知識が必要になります。
人事や総務にかかわる方は、これまではなんとなく「障害者雇用」を進めなければならないことは理解していたかもしれません。
実際に障害者雇用の担当者になると、障害者雇用の納付金申告や6.1報告また受け入れや助成金申請など幅広い知識と実務が求められます。
障害者雇用担当者が手続きを怠ったため、企業は膨大な金銭的ペナルティを支払うこともあったりします。
ここでは障害者雇用に関わる基本的なこと、かつ必要なことをお伝えしていきます。
障害者に関する法律を理解する

日本の障害者雇用は、「障害者雇用促進法」(正式名称「障害者の雇用の促進等に関する法律」)に基づいて行われています。
企業においてはまず、障害者法定雇用率を満たさないといけません。
50名以上を雇用する事業主には身体・知的・精神障害の雇用が義務づけられています。
障害者雇用納付金制度を理解する
現在の障害者雇用率は2.3%(2021年3月改正)、つまり従業員43.4人に対して1人の障害者を雇用することが定められています。
今後、この法定雇用率は上昇することはあっても下がることはありません。
障害者雇用は、事業主が果たしていく社会連帯責任の理念に立ち、障害者雇用に伴う経済的負担の調整を図っています。
そのため、障害者雇用率に達していない企業は「障害者雇用納付金」未達分について金銭で負担していただくことになっています。
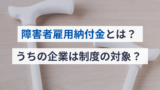
障害者雇用納付金とは障害者の法定雇用未達成1名につき月50,000円を支払います。
逆に障害者の法定雇用を上回った企業に対しては1名につき月27,000円の調整金が頂けます。
障害者雇用が未達成の企業は納付金を払えば終わりではなく、毎年6月1日の障害者雇用状況報告(いわゆる6.1報告)で障害者の雇用率が大きく下回る企業に対して「雇い入れ計画」の提出を求められます。
また、「雇い入れ計画」に対して取り組まない企業については「企業名公表」となります。
障害者手帳とカウントを理解する

企業において雇用義務のある障害者とは、障害者手帳(身体、知的、精神)を保有する人が対象となっています。
障害の種類については身体障害、知的障害、精神障害があります。
障害者手帳は「身体障害」「知的障害」「精神障害」の3通りがあり、それぞれ「身体障害者福祉法」「知的障害者福祉法」「精神保健福祉法」により規定されています。
身体障害者
身体障害者福祉法では、「身体上の障害がある18歳以上の者であって、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう」と定義されており、大きくは視覚障害、聴覚・言語障害、肢体不自由、内部障害、難病などが含まれます。
知的障害者
知的障害者福祉法では、「知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別の援助を必要とする状態にあるもの」と記されています。
知的障害者に交付される手帳は「療育手帳」であり、各自治体の基準によって判断されています。
知的障害者の区分については「最重度」「重度」「中度」「軽度」の4つの区分を設けています。
精神障害者
精神保健福祉法は「統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者」と定めています。
精神障害の種類は大きく、統合失調症、気分障害、てんかん、発達障害などの多岐にわたります。
精神障害者手帳の等級は、1級から3級までの3つの区分に分けられており1級が重度になります。
精神障害者手帳は、有効期限が2年で2年に一度更新手続きが必要です。
この更新を行わないと手帳を所持していないことになり、障害者としてカウントされません。
障害者雇用に関する助成金を理解する
障害者の雇用を促進するために助成金制度や優遇措置が設けられています。
- 特定求職者雇用開発助成金
- 障害者トライアル雇用奨励金
- 障害者短時間トライアル雇用奨励金
- 障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金)
- 特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)
- 障害者職場定着支援奨励金
- 障害者雇用安定助成金(障害者職場適応援助者・ジョブコーチ)
すべてを把握することが難しいので、企業の実情にマッチする助成金を選ぶようにしましょう。
助成金によっては申請できる時期が限られていますので、ホームページで詳細を調べるかまたはハローワークなどで確認することができます。
ハローワークには必ず「障害者雇用の専用デスク」というものがありますので、専門スタッフのアドバイスを無料で受けることができます。
障害者を雇い入れの方法
障害者の雇用をはじめたいと思っていても、実際、求人活動をどのようにすればいいのかわからないというご意見が多数寄せられます。
障害者の求人にあたっては以下の機関の特徴などを見ながら検討してください。
ハローワーク
ハローワークは企業が障害者雇用を進めることができるように、あらゆる相談を受けつけしています。
ハローワークの求人掲載は「障害者求人」として掲載されるので、ここからの応募件数が圧倒的に多いと言えるでしょう。
近年はハローワークのネット求人サイトが充実しており、初回の企業登録さえ済ませばあとは求人内容や就業先、労働条件などネット上で更新ができるのですごく便利なツールとなっています。
就労移行支援事業所
就労移行支援事業所とは、障害福祉サービスのひとつである「就労移行支援」を提供する事業所のことです。
ハローワークに求人票を掲載した場合、地域の就労支援事業所の通所者から応募があったりします。
就労支援事業所は事前連絡により見学が可能です。
地域の就労支援事業所の担当者とはごあいさつや名刺交換などをして日頃からのつながりもプラスアルファの要素となります。
就労移行支援事業所大手2社
障害者就業・生活支援センター(ナカポツ)
就業及びそれに伴う日常生活の仕事と生活の両方をサポートするセンターとなっています。
スタッフは「就労支援員」と「生活支援員」がおり、就職を希望する障害者または在職中の障害者の抱える問題について支援を行うのが特徴です。
こちらも同様、ハローワークに求人票を掲載した場合、障害者就業・生活支援センターに通所されていいる方(又は担当者)からの応募があったりします。
その他(障害者求人媒体)
ここ数年障害者雇用に関しての企業の取り組みが改善され、障害者求人も活発になってきました。
求人サイトでは、障害者雇用に関しての新たなカテゴリーが導入されたり、障害者雇用専門の求人誌も登場するようになりました。

また、農園型障害者雇用サービスという新たなビジネスモデルも徐々に増えつつあります。

雇い入れ後の継続安定施策について
障害者雇用担当者チェック事項
チェック内容
- 常に勤怠管理を行う(月間実働時間を把握する)
- 定期面談、不定期面談を実施する
- メールやSNSで近況報告や悩み相談を受け付ける
- 職場環境や人間関係を定期的にヒアリングする(就業先の上長や同僚から)
提出書類(大きくは年2回)
- 障害者雇用納付金申告申請書(提出期限:毎年4月1日~5月中旬頃)
- 障害者雇用状況報告【いわゆる6.1報告】(提出期限:毎年6月1日~7月中旬頃)
【注意】~障害者雇用納付金は2~3年に1度「調査」があります。
「障害者職業生活相談員研修」を受講しよう
障害者職業生活相談員資格認定講習は、各都道府県内の会場で毎年実施されます。
日程についてはホームページ又は管轄のハローワークで調べることができます。
講習の内容は以下の通りです。
- 障害者雇用の理念
- 障害者の雇用の現状と課題
- 関係行政機関と障害者対策
- 障害者職業生活相談員
- 障害者の心理、職業能力
- 施設・設備の改善
- 労務管理と人間関係管理
- 適職の選定と職業能力の開発
- 職場適応の向上
- 意見交換会、事業所見学、支援機関見学等
※プログラム内容は、各都道府県の会場によって若干変わることもあります。
まとめ
今回は障害者雇用担当者の業務について触れてみました。
障害者雇用担当者の業務は意外と知っているようで知らない内容も結構多いのがわかりました。
障害者雇用は提出書類も多く、何よりも常日頃のこまめなチェックやケアが必要だということがわかりました。






















コメント